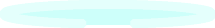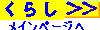社会福祉事業法等一部改
正法案大綱が、四月十五日
に厚生省から出された。こ
の大綱にもとづき、厚生省
が進める「社会福祉基礎構
造改革」の法的根拠となる
社会福祉事業法等九法の
「改正」案が、今国会に上
程される予定となってい
る。法案が可決・施行され
ると、わが国の社会福祉を
大きく後退させていくバネ
の役割を果たし、社会福祉
の理念そのものを変質させ
ることは明らかである。
四つの柱
そもそも社会福祉におけ
る「基礎構造」とは何をい
うのであろうか。まず第一
は、社会福祉ニーズにたい
しどのような供給体制をと
るかという柱である。大綱
骨子は「多様な事業主体の
参入促進」を旗印に、営利
を目的とした「民間企業な
ど社会福祉法人以外の参入
を認めること」を方向づけ
ている。福祉分野が企業の
営利追求の新たな産業・事
業分野として位置づけられ
ている。
第二の柱は、社会福祉サ
ービスの利用のしくみであ
る。大綱では、現在まで社
会福祉制度の骨格を担って
きた措置制度(国・自治体
の社会福祉サービスの給付
・提供の義務・責任を明確
にした制度)から、民法上
の契約制度に切り替えよう
としている。
第三の柱は、費用負担の
体系である。現在の保育料
のように保護者の所得水準
に応じた「応能負担の原則」
から、利用内容に応じた定
額制をベースにした「応益
負担の原則」に切り替えよ
うというのが基本方向であ
る。
第四の柱として、権利保
障体系があげられる。「基
礎構造改革」が持ちだす「権
利擁護」とは、導入しよう
とする「契約制度」を「補
完」するもの・・たとえば
「成年後見制度」 (本人に
よる契約手続きが困難な場
合、後見人を認める)など
・・なのである。憲法の生
存権保障体系であるべきも
のが、民法的権利内容にわ
い小化されている。
買い取り
大綱では、身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法、
児童福祉法(障害児に限る)
における福祉サービス利用
のしくみを、現行の措置制
度から、「利用者が福祉サ
ービスの提供者と直接契約
し、市町村がその費用につ
いて支援費を支給する方式
に改めること」が示されて
いる。厚生省はこれまでも
繰り返し、直接契約は利用
者の選択権を保障するシス
テムである、と強調してき
た。しかし、特別養護老人
ホームの待機者が約十一万
人、保育所の待機児童が四
万人という現状である。選
択権保障の前提条件が整備
されていないことは明らか
である。
「支援費」支給のシステ
ムは、大綱では、施設の利
用料から自己負担額(利用
者の所得に応じランクづ
け)を引いた差額を支給す
るというもの。現行の「国
庫負担・補助金」から、「公
的助成」 (「中間まとめ」
段階)、そして「支援費」
(「大綱」)への文言変化
は、費用負担における公的
責任の後退を意味してい
る。将来的には、競争原理
にもとづいて事業体ごとの
利用料が設定され、どの程
度の自己負担ができるのか
によって、享受できる福祉
水準が決まるという、いわ
ば自己努力による福祉「買
い取り」システムが予定さ
れているのである。
「基礎構造改革」の方向
は社会福祉を国家責任か
ら、私人間の契約関係に切
り替えることによって、福
祉を政治課題からはずすこ
とになる。つまり、社会福
祉充実の要求の矛先は各事
業体に向けられることにな
る。国・自治体の責任は不
問に付されることも、「社
会福祉基礎構造改革」のも
うひとつの隠されたねらい
なのである。
社会福祉事業法等の「改
正」と介護保険の施行が予
定どおりおこなわれると、
二〇〇〇年四月から、高齢
者福祉分野は介護保険制
度、障害児・者福祉分野は
直接契約方式を基本にした
契約制度になる。保育所は
「保育の実施」制度(市町
村の「保育に欠ける子ども」
の保育保障義務は明確に存
在している)、児童養護施
設などの養護系児童福祉施
設は現行の措置制度の存続
・・と、これらのシステムが
併存することになる。
こうした制度の複雑化
は、分野によって権利の保
障システムと水準が大きく
異なる状況をつくりだす。
保険料を支払う方式であっ
たり、直接契約をして支援
費を受けるシステムであっ
たり、社会福祉施設利用に
伴う利用料を所得水準によ
って支払うなど、福祉ニー
ズによって大きな違いが生
じ、申請も複雑になる。簡
便で利用しやすいという手
続き上の権利保障の点から
も、問題がある。
今後の政府・厚生省の基
本戦略は、規制緩和の名の
もとに民間企業の参入をお
こない、市場主義的競争原
理を社会福祉に徹底して導
入することである。こうし
た方向は、社会福祉分野に
おいて優勝筋敗の鉄則が貫
徹されることで、地域密着
型の小さな事業体が追い出
され、資本力の大きな民間
企業が闊歩(かっぽ)する
ことになろう。その結果、
身近な福祉を利用しようと
する際、高い利用料を払わ
ざるをえない事態が想定さ
れるのである。
契約制度
「基礎構造改革」は、本
来のねらいを押さえた上で
今回の法「改正」では障害
児・者福祉分野に契約制度
を導入することに力点を置
いている。
母子生活支援施設につい
ては「現行の措置制度から、
利用者が待望する施設を都
道府県に申し込み、利用す
る制度に改める」という入
所方式の見直しがおこなわ
れている。さらに運用事項
として、保育所への民間企
業の参入を認めることで、
福祉の市場化に向けて風穴
をあけている。特別養護老
人ホームについては、介護
保険導入後に方向を出すこ
とになっているが、高齢者
福祉分野においても福祉の
市場化は政府の既定方針と
なっている。
こうした方向は、憲法第
二五条(国民の生存権保
障)、第一三条(幸福追求
権)にもとづいた社会福祉
の理念である無差別・平等
の原則、健康で文化的な生
活保障の原則を大きく崩す
役割を果たすことになろ
う。とくに民間営利企業の
参入は、高い水準の福祉は
お金で買うという市場原理
の広がりを意味している。
福祉の権利を優先して保障
されるべき貧困・低所得階
層が社会福祉から排除され
ることになる可能性が高
い。
それは権利としての社会
福祉の空洞化であり、高い
金を出せる人は高水準の福
祉を享受できて、あまり自
己負担できない人は低福祉
で甘んじなければならない
という社会福祉の理念の逆
転現象を生み出すことにな
るのである。
「社会福祉基礎構造改革」
は国民各階層が総力をあげ
てとりくむべき緊急かつ重
要課題であり、権利として
の社会福祉を守り、発展さ
せていく上で避けて通れな
い国民的運動課題になって
いるといえよう。
あなたのご意見・感想・メッセージの送り先: ksk@po.incl.ne.jp

 ・生健会への案内
・生健会への案内
 ・ページ全体のご紹介(初回時必見)
・ページ全体のご紹介(初回時必見)