
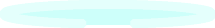

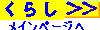
(98年 1月 24日付「守る新聞」)
今年は国際高齢者年
お年寄りが喜べる社会を
全国老後保障地域団体連絡会事務局長 上坪 陽
医療費の自己負担がふえ、年金の支給額はへらされる −−日
本の高齢者をとりまく状況はきびしいです。九九年は国連が定
めた「国際高齢者年」です。高齢者いじめの政策がすすめられ
るいま、その理念に耳をかたむけたいと思います。国際高齢者
年・日本NGO会議の呼びかけ人で、全国老地連事務局長の上
坪陽(かみつぼ・ひかり)さんにお話をうかがいました。
一番気に入っている理念があるんです。「高齢者は植物のように枯れて死んでいくのではない。死ぬまで発達するんだ」というものです。一九九一年に国連が決めた「高齢者のための国連原則」の中でこんなことが述べられているんですね。具体的には「自己実現」と表現されます。
こうした考え方は、これまでの日本にはなかったものです。二十年前ですが、私はある講演で老人ホームの職員を前に「子どもが発達するように、高齢者も発達するんだ」と言ったら、笑われてしまいました。日本ではこの程度の認識だったのです。
「国連原則」は、「参加」をうたっています。自己実現をはかるために、仲間をつくろうというわけです。自分たちの願いを実現するために、運動団体をつくることができなければならないと強調してい
るのが特徴です。国際高齢者年の理念を示すものとして、この「国連原則」は押さえておくべきものです。
若い世代の参加を
日本では、高齢化社会というと暗いイメージで語られがちです。
高齢者をやっかいものにし、高齢化社会危機論がふりまかれています。国際高齢者年はそうではなくて、「高齢者を社会発展の原動力に」が理念とされています。
また、「すべての世代のための社会をめざして」という合言葉が掲げられています。決して高齢者だけがとりくむものではないと、とりわけ若い世代の理解と参加を求めています。
だから現役の労働組合などは、積極的にとりくんでほしいですね。高齢者は年を取ってから体を壊すのではありません。現役の時の健康管理こそが大切です。組合員の人生にかかわっている運動と認識してほしい。
組合を卒業した高齢者たちから連帯のあり方などを学んではしいものです。
一九九一年高齢者のための国連原則(抜粋)
独 立
一条 高齢者は、所得の保障と家族および地域社会の支援と自助を通じて十分な食糧、水、住居、衣類、健康へのケアが得られなければならない。
(二条省略)
三条 高齢者は、職場から引退する時期と退職するペースの決定に参加できなければならない。
(四−六条省略)
参 加
七条 高齢者は、社会との結びつきを維持すべきであり、高齢者の福祉に直接関係する政策の立案および実施に積極的に参加すべきである。また、高齢者の知識や技能を若い世代と共有すべきである。
八条 高齢者は、地域社会に役立つ機会を見つけ、広げることができるべきであり、高齢者の関心や能力にふさわしいボランティアとして役立つことができなければならない。
九条 高齢者は、高齢者の運動あるいは団体をつくることができなければならない。
ケ ア
十条 高齢者は、文化的価値に関する各社会の制度にしたがって、家族や地域社会のケアと保護から利益を得られなければならない。
(十一−十四条省略)
自己実現
十五条 高齢者は、自分の可能性を最大限伸ばすことのできる機会を追求することができなければならない。
十六条 高齢者は、社会の教育的、文化的、精神的そしてレクリエ」ソョンに関する資源を利用できなければならない。
尊 厳
十七条 高齢者は、搾取ならびに身体的あるいは精神的虐待を受けることなく、尊厳を保ち安心して生活できなければならない。
十八条 高齢者は、年齢や性別、人種的または民族的背景や障害またはその他の地位にかかわらず公正に扱われ、高齢者の経済的寄与とは関係なく評価されるべきである。
【解説】 「国際高齢者年」は一九九二年の国連総会で定められました。「さらなる人生の充実」を求める人びとによって、二十一世紀を高齢期間題へのとりくみを強化するなかで迎えようとする国際世論と、それまでの活動の積み上げを背景にして決定されました。
一九九一年に採択された″高齢者の原則″は、一九四八年、国連総会にアルゼンチン政府によって提案された「高齢者権利宣言案」が発端になっています。

 ・生健会への案内
・生健会への案内