

経済「これって何」?
「しんぶん 赤 旗」(日曜版)1999年 1月31日」
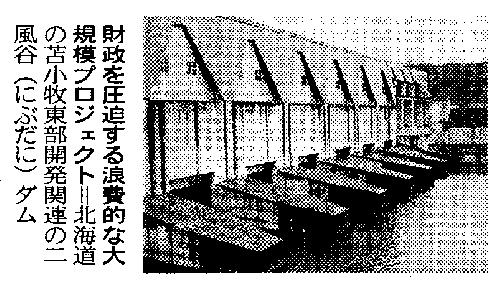
巨額の財政赤字は、将来の
増税を予測させて消費を冷や
したり、住宅ローンの金利上
昇につながるなど景気と生活
に直接はねかえってきます。
大蔵省によると、一九九九
年度末の国の借金である長期
債務残高は四百四十六兆円、
地方の借入金残高は百七十六
兆円で、重複分をのぞいた合
計は六百兆円にのぼります。
これは国内総生産(GDP、
約五百兆円)の一二〇%の規
模で、一世帯あたり約一千三
百万円の借金に相当します。
国の借金の大半を占めるの
が公共事業にあてられる建設
国債と、ほかの物件費など経
常経費にあてられる特例国債
(赤字国債)で、このほかに特
別会計の借入金などが含まれ
ます。国の歳入に占める国債
発行額の割合を示す「公債依
存度」は、九八年度が三八・
六%、九九年度は当初予算案
の段階で三七・九%に達して
います。これまで最悪だった
七九年度の三四・七%(決算ベ
ース)を大幅に上回ります。
地方の借入金の大半を占め
る地方債(返済が二年以上に
またがる借金)は、国が公共
投資の積み増し政策に地方自
治体を動員してきたため、九
二年度以降に急拡大しまし
た。ある民間研究機関の試算
によると、九一~九六年度に
増加した地方債残高の六割以
上が国の景気対策による増加
分だとしています。
その結果、一般財源(地方
税、地方譲与税、地方交付税
の合計)にたいする公債費(地
方債の元利金の支払いなど)
の負担割合を示す公債費負担
比率は、財政の黄色信号とさ
れる一五%に迫る一四・〇%
となっています(九六年度)。
財政制度審議会(蔵相の諮
問機関)は、九五年十二月の
報告で、国と地方を合わせた
長期債務残高の対GDP比六
〇%以下というEU(欧州連
合)の通貨統合への参加条件
について、「通貨価値安定の
ための一つの客観的条件」と
のべています。そのうえで、
日本の当時の水準(八八・九
%)について、「現状は例え
て言うならば、近い将来にお
いて破裂することが予想され
る大きな時限爆弾を抱えた状
態」と指摘しました。
同審議会は九六年七月にま
とめた「財政構造改革を考え
る」で、国と地方の長期債務
の対GDP比が十年後には一
二六%に達すると警鐘を鳴ら
しました。実際はわずか三年
で一二〇%になり、この間の
浪費と無駄遣いのすさまじさ
を示しています。
EUの通貨統合の財政にか んする条件としては、もう一 つ、国と地方の単年度の財政 赤字が対GDP比で三%以内 という基準があります。これ らの基準の関係はつぎのよう なものとされています。今後 の名目成長率を五%程度と見 込むと、長期債務のGDPに たいする比率六〇%と利払い 費のGDP比を増加させない ためには、財政赤字のODP 比は三%以下にする必要があ る--。
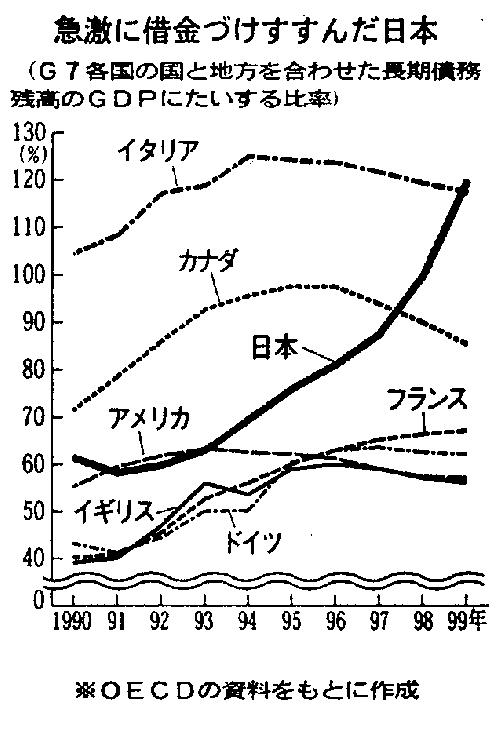
日本の場合を同様に計算す
ると、財政赤字の対GDP比
が六・〇%を超えれば、長期債
務と利払い費のGDP比がい
ま以上に増えてしまいます。
九九年度の国と地方あわせた
財政赤字のGDP比は九・二
%の見込みで、「爆弾」の破裂
に突進している状態です。「五
%成長」でもこの深刻さで、
小渕首相がいうように「経済
が回復してから検討」ではま
ったく間に合いません。
財政赤字の大もとは、国と 地方あわせて社会保障に二十 兆円、公共事業に五十兆円と いう逆立ちした財政の使い方 です。財政を再建するには、こ こに大胆にメスをいれる必要 があります。日本共産党の不 破哲三委員長は二十一日の衆 院代表質問で、①公共事業の 規模半減を目標にその計画的 実現を②社会保障制度への国 の負担の抜本的な拡大を③地 方政治でも開発中心主義から 住民サービス本位への転換を ④教育・福祉など国民生活密 者型に公共事業の重点を移す --の四点を提案しました。 平田和宏 記者

 hirotaのこだわりの課題
hirotaのこだわりの課題