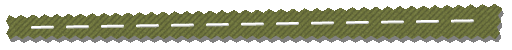
副園長 釜土蘭子
| 最近では「キャンドルサービス」というと結婚式の披露宴で行うものの方がだんだん有名になってしまいました。新郎新婦が一つ一つのテーブルに火をともしていく演出です。 インターネットで調べると、「東京オリンピックの頃から行われるようになった」とか「七〇年代にろうそく製造会社の社員の結婚式で行ったのがはじまり」とかいろんな説がありました。ロマンチックな雰囲気が受け入れられて、広く行われるようになったのでしょう。 けれども七尾幼稚園で、いえ、キリスト教会ではそれよりももっと前から「キャンドルサービス」という言葉を使ってきました。英語ではcandlelight service というのが正しいのです。serviceは、「礼拝」という意味がありますので、ろうそくの火をともして行う礼拝のことです。燭火礼拝と訳されることもあります。多くの教会でクリスマスイブ十二月二十四日の夜に、ろうそくの火の下で礼拝を守ります。そして七尾幼稚園では、クリスマス会の日の礼拝を、キャンドルサービスとして守ってきたのです。礼拝堂に入ったAぐみさんが園長先生から火をもらい、それを持ったままで礼拝を守る。それをずっと行ってきたのでした。 それは昨年のクリスマス会の3日前の事でした。私は、クリスマス会の準備をしながらこんな事を考えていました。 「来年は礼拝堂が工事中になる。礼拝堂がなければキャンドルサービスはできない。この礼拝堂でする幼稚園の最後のキャンドルサービスを思い出多い、意味深いものにしたい。」 8月に壊された、あの礼拝堂でずっと続けられてきた幼稚園のキャンドルサービス。それが最後だと思うと感慨深いものがありました。また、礼拝堂あってこそのキャンドルサービスだと思っていたので、礼拝堂の無い時にはキャンドルサービスは行わない事になると考えていたのです。 そんな私に、Aぐみの担任の澤田先生からある相談がありました。「Aぐみの女の子の一人が火を持つのが怖いと言っています。ろうそくを持たずに礼拝に出てもいいでしょうか。お家の方も心配しておられるので・・・」というものでした。 心配がわからないわけではありません。ろうそくとはいえ、「火」です。そんなこわいことはしたくないとまず思っても無理かもしれません。でも一人だけ持たないのはどうだろう?手のケガなどが理由なら仕方がないが、こわいからという理由でやめてしまうのはどうだろうか。 澤田先生、園長先生、堂脇先生そして他の先生達とも相談して、その女の子が自分で火を持とうと思えるようにお話をしてみることになりました。でもその子だけにお話するのはおかしな事になります。Aぐみさんみんなを礼拝堂にきてもらって、なぜろうそくの火を持って礼拝をするのかというお話をすることにしたのです。 「クリスマスはイエス様のお誕生日だよね。イエス様がこられたのは、神様がみんなのことを大好きだよ、愛しているよっていう意味なんだよ。神様からの大きなプレゼントなんだ。神様から愛されている事、それをうれしいなと思ってほしい。イエス様は、みんなの心を照らす光としてきたんだ。だから、クリスマスの礼拝では、光を、ろうそくの火として一人一人もらうんだよ。」 「だけど、小さいお友達はまだろうそくを持つことはできないよね。まだ小さいから火は持てない。でもAぐみさんは、もう大きくなったよね。ちゃんと光をもらうことができる。だからみんなでろうそくをもって、光をもらおうね。できるよね。」 Aぐみさんみんなが大きくうなづいてくれて、こわがっていた女の子もみんなと同じ事をしようという思いになってくれました。 そして、クリスマス会の当日。いつもの年より緊張してろうそくを持っていたようなAぐみさんの姿がありました。ああ、よかったなと思いました。 けれど、実はちょっと自分の髪の毛を焦がした男の子もいたのです。 クリスマス会の数日後、その男の子のお母さんとゆっくりお話しする機会がありました。私としては、クリスマスにいやな思い出が残ってしまったのではないかとちょっと心配し、お母さんに率直にお詫びをしたかったのです。 ところがそのお母さんから返ってきた言葉は、「キャンドルサービス、良かったです」だったのです。お母さんも学生時代にキャンドルサービスをしたことがあった事、それが自分にとってとても大事な、忘れられない経験だったこと。その同じ経験を息子がしてくれて喜んでいること。そして、このキャンドルサービスを是非これからも続けてくださいと言われたのでした。 こんなクリスマス会が終わった後、私は「来年もキャンドルサービスをする!」と職員室で宣言しました。礼拝堂が無くてもキャンドルサービスをしなくてはならない。それをぬきにして、七尾幼稚園のクリスマス会はない。礼拝堂がないから、その年のAぐみさんだけがキャンドルサービスをしなかった、なんて事は、やはり違うのだと考えたのでした。 なんとなくかっこいいからしているのではない。なんとなくロマンチックだからやっているのではない。七尾幼稚園の教育の中でとても大きな意味を、キャンドルサービスは持っているのだ、それを去年のAぐみさんとそのお家の方々を通して教えられのでした。 キャンドルサービスでは、一人一人が園長先生から「火」をともしてもらいます。 「火」をもらうことには大きな責任が伴います。ちゃんと持っていなくてはいけません。おふざけしたら危ないのです。 それは、私たちが人生の中で大事なものを受け取る時、大きな責任を負うのと似ています。生涯の伴侶を得る時、我が子を授かる時、自分の仕事を持つ時、そんな大事な宝物を得るときには必ず大きな責任が伴うのです。「こわいからいらない」と言っていたら、臆病で無責任な生き方になってしまうかもしれません。 大事なものであるからこそ、責任を持って受け取る。おそれもあるかもしれない。けれどおそれを伴うほどの宝物を受け取る勇気が人生には必要なのです。 ろうそくの火をおそれつつ大事に持った記憶。それは子供達に大切なことを教えるのです。 園長先生から受けとった火が広がって明るくなっていきます。一人の人から広がっていく火。最初は一つしかない火が増えていく。その美しさは子供達の記憶に残ることでしょう。神様からの愛をうけとって、それが広がっていくすばらしさを感じてほしいのです。 「愛されていることを知り、 愛する者となるために」 この教育目標を、キャンドルサービスほど物語るものはありません。 だから、ちょっと大変なのですが、ホールのいすの並べ方をがらっと変えて、今年もキャンドルサービスをします。 狭い中でするので、ご家庭の皆様にはご迷惑をおかけします。でも大事な大事な事を子供達に伝えたいのです。よろしくお願いします。 |
 今月のトップページへもどる
今月のトップページへもどる