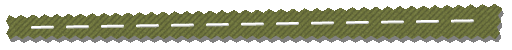
やりたいことと」
園長 釜土達雄
| どうでもよいことですが、わたしは大学を2つ出ています。最終的に行こうとしていたのは、二番目の大学で、それは牧師養成の単科大学の東京神学大学でした。一年生から大学院の博士課程までを含めても二〇〇人に満たない、当時は日本で二番目に小さい大学でした。 しかも、一般的に他の大学を出てからの入学やいったん社会人を経験してからの入学が推奨されるという不思議な大学です。牧師という役職がそうさせるのですが、一年生の入学生よりも、他の大学を出てからの三年編入の学生が多い大学だったのです。 そういうわけで、最初の大学では自分が学んでみたい勉強をしてみることが許されました。それではとわたしは、生物学や気象学や作物学といった小学生時代から興味のあった総合的な学びが出来る農学科を選んで在籍していたのでした。 そもそも、小学生時代から得体の知れない昆虫のことをやたらと知っていて、理科部の変わり者だったわたしは、昆虫学をちゃんと勉強してみたいと思っていました。 青虫がちょうちょになるそのさなぎの時期に、どのように身体が変化するのか。不思議でしようがなかったのです。蟻が規則正しい社会生活を営んだり、ミツバチが同じように社会性をもっていたり。それにもかかわらずすべての蟻やすべての蜂が同じように社会性をもっているわけでもない・・・。そんな一つ一つが不思議だったのです。 種のことも不思議でした。だいたい秋になって草むらを歩くとたくさんの雑草の種が洋服につきました。とれた種がシャツの中にまで入ってきて、ちくちくして痛くてしようがありません。ところが、稲刈り前の田んぼの中を歩いてみても、稲の種が洋服につくとこはないのです。稲の先っぽがシャツを通ってちくちくすることはあっても、種がとれてシャツの中にまで進入してくることはありません。小さい時から、「なぜ稲の種は、とれないのだろう?」と不思議でしようがなかったのです。 お天気のことも不思議でした。なぜこちらは晴れているのに、あちらは雨なのか。冬なのに暖かかったり、夏なのに寒かったりするのだろう?天気予報のおじさんは、なぜ明日の天気がわかるのだろう?不思議に思うことはいっぱいありました。天気予報のおじさんの予報が、大外れすることも、不思議でした。 大学進学の時期に、いろんな大学の学科を調べていたら、こんなへんてこりんな疑問を全部扱う学科が「農学科」だったのです。 ところが進学してみて自分の勘違いもいっぱいあることに気づきました。たしかに農学科で昆虫学は扱いますが、それは理学部の昆虫学とはかなり違います。理学部の昆虫学は基礎学としての昆虫学ですが、農学科の昆虫学は病害防除としての昆虫学。作物を昆虫から守るための昆虫学です。すなわち簡単に言えば、昆虫を殺す方法を学ぶ昆虫学なのです。 農業気象学も、一般気象学とはかなり違います。気象学の教授は「よその田んぼの天気はどうでもいい。自分の田んぼの天気を当てろ」。と繰り返していました。「それによって、何をしなければならないか、農作業の手順が変わってくる」。おっしゃるとおりです。 おもしろかったのは、作物の品種改良の歴史でした。バナナや稲がどのように品種改良が進んだかを、丁寧に教わりました。バナナの原種には種があること。バナナの種がなくなるのに、どれだけの時間と、品種改良の努力がなされたか。稲の品種改良の最大のものは、実った種が落ちないようにすること。その改良に、どれだけの時間がかかったか。わくわくするような時間でした。 当然農学科ですから、農場実習が基本。農作物を作ったり、家畜の世話があったり。食品加工をしたり。 わたしがどんたくやユニー、中島ストアーに出没して野菜をひっくり返してみているのは、こんなルーツがあるからです。ついつい野菜や冷凍品の品定めをしてしまう。 今はありませんが、以前は礼拝堂の後ろにロッカーを加工したスモーカーがありました。そこでスモークチキンやベーコンを作っていたのです。 自分で食べるものを、自分で作る。それは、どれほどの贅沢だろうかと、いつも思います。 けれどもこの最初の大学で、幼児教育学を学んでいたわけではありませんでした。教職課程をとっていましたが、理科とか農業の先生になる過程。それもとてもおもしろかったのですが、幼児教育とは全くの無縁でした。 わたしが幼稚園の仕事をするきっかけとなる幼児教育について教えられたのは、2つめの大学に入ってからでした。もちろん、牧師養成の単科大学ですから幼児教育を専門に教えるわけではありません。牧師として赴任する教会に、幼稚園や保育園があることが多く、また牧師が園長として招かれることも多いので、学生にしっかり教えておこうと、専門の先生が招かれていたのです。 今年の一月二八日に、キリスト教保育連盟北陸部会の園長・主任研修会がありました。講師は北陸学院大学学長の三浦正(みうらまさし)先生。この先生こそ、わたしが幼児教育を志すきっかけを作ってくださった先生でした。 だいたい、三浦先生が金沢にいらっしゃったこと自体が驚きでした。だってその前は,静岡英和学院大学の学長だったのです。なぜ北陸にいらしたのかしらと思っていたら、北陸学院短期大学を北陸学院大学にするため。そのために招かれたのが三浦先生だったのです。 北陸学院以外でお会いするのは久しぶりでしたのでご挨拶を申し上げて、何人かの方に、わたしも三浦先生に習ったのですと申し上げました。知らない人は、三浦先生と釜土先生がどうして?という感じでしたが、先生はいっこうに意に介さず、「はい、釜土君はちゃんと授業を聞いていました」。 研修会の二時間にわたる講演は、大学の授業そのものでした。発達段階をしっかり踏まえ、幼児教育に何が必要か、情熱的に語る三浦先生。青春時代がよみがえってきて、あつい心になるそんな講義でした。 「しなければならないこと」が 「やりたいこと」になる。 もしそうなったら、それは、 人生の喜びそのものとなるでしょう。 多くの場合、「しなければならないこと」と「やりたいこと」は違うのです。 「しなければならないこと」は「やりたくないこと」で、仕方なく、しなければならないからと、我慢しながらやるのです。いやいややるのです。だいたい、学校での勉強なんて、そういうものなのだと、みんなあきらめている。そして先生も、「テストに出すよ」なんと脅して、勉強させようとする。 けれども世の中には「やりたいこと」もあって、それはだいたい、「しなければならないことではないこと」なのです。自分の楽しみであって、生活の糧にも結びつかず、自分の成長にも無縁のこと、勉強など、したいことのはずがないなどと考えてしまうのです。 わたしはどれほど幸いだったかと思います。小さい時から、自分が不思議だと感じたことを、「世の中には不思議なことがいっぱいある」と、教えてくださった人がいた。 わたしはどれほど幸いだったかと思います。小さい時から、知識を得るだけではなく、「自分の頭で考えてごらん」と、教えてくださった人がいた。 わたしはどれほど幸いだったかと思います。小さい時から、わたしには興味もないのに、自分がおもしろいと思ったことを、一生懸命「おもしろい」と、一人で勝手に情熱傾けて話してくれる人がいた。 そんな一つ一つの経験が、学ぶことは「しなければならないこと」だけれど、「してみておもしろいこと」「してみたらたのしいこと」「したいこと」「やりたいこと」になっていくことを、体感してきたのです。そんな経験がどれほどの宝となったことでしょう。 「しなければならないこと」が 「やりたいこと」になる喜び。 そんな喜びの一つ一つを、 教えてくださった一人一人の恩師に、 感謝。 答えを教えてしまいます。 だけど、大事なところは外してはいけません。考えて考えて迷うからこそ、大事なことを知ることが出来るのです。 |
 今月のトップページへもどる
今月のトップページへもどる